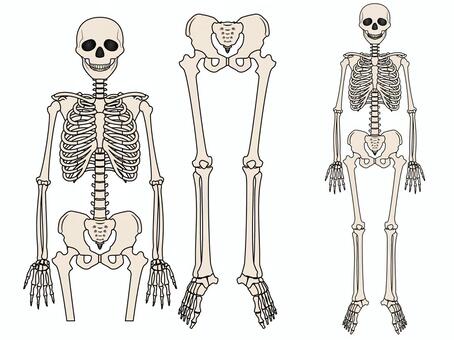2025年7月27日放送のEテレ「未病息災を願います」で、骨密度の低下を防ぐための食事法と運動法について紹介されました。
番組では、秋田大学の宮腰尚久教授が、自覚症状のないまま進行する骨密度の低下、通称「静かな病気」のリスクと、今日から始められる具体的な対策を詳しく解説していました。
骨の健康を守るための知識を深めていきましょう。
骨密度が下がるとどうなる?
骨の健康は日々の生活に直結しますが、骨密度が低下しても初期症状がないため見過ごされがちです。
ここでは、骨密度が低下した際に体に起こる変化と、それに伴うリスクについて解説します。
骨密度が低下すると、骨がもろくなり、自覚症状がないまま骨折のリスクが著しく高まります。
これは、骨の内部がスポンジのようにスカスカになり、外側の壁も薄くなってしまうためです。
痛みなどの自覚症状がないまま静かに進行することから「静かな病気(サイレント・ディジーズ)」とも呼ばれています。
体に起こる変化としては、「背が少し縮んだ」「姿勢が前かがみになった」などが挙げられます。
これらは、背骨が気づかないうちにつぶれるように変形する「圧迫骨折」が起きているサインです。
また、軽く手をついただけ、あるいは些細な転倒で手首や腰を骨折してしまう「脆弱性骨折」も増加します。
特に、将来の歩行困難や寝たきりの原因となる大腿骨の骨折は、最も避けたい重大なリスクです。
原因は加齢だけではなく、運動不足、栄養の偏り、過度な飲酒といった生活習慣が大きく影響しています。
骨密度を保つための食事のコツ
骨の健康を維持するためには、日々の食事が非常に重要です。
骨の主成分となる栄養素を効率的に摂取し、骨密度の低下を防ぐための食事のポイントを紹介します。
骨密度を維持する鍵は、「カルシウム」「ビタミンD」「ビタミンK」という3つの栄養素をバランス良く摂取することです。
カルシウムは骨そのものを作る主成分であり、ビタミンDはカルシウムの腸での吸収を促進します。
そして、ビタミンKは吸収されたカルシウムが骨に沈着するのを助ける役割を担っています。
これら3つの栄養素をセットで摂ることが、強い骨を作るための基本戦略です。
具体的な食材としては、カルシウム源として吸収率の高い牛乳やヨーグルト、チーズといった乳製品が最も手軽です。
さらに、納豆や豆腐などの大豆製品、ししゃもやちりめんじゃこといった骨ごと食べられる小魚も非常に有効です。
カルシウムの吸収を助けるビタミンDは、サケやイワシなどの魚類、きのこ類、卵に豊富に含まれています。
また、ビタミンDは日光を浴びることで体内でも生成されるため、日中に少し散歩するだけでも効果があります。
骨へのカルシウム定着を促すビタミンKは、納豆に特に多く含まれるほか、小松菜やブロッコリーなどの緑黄色野菜からも摂取できます。
摂取方法のコツとして、カルシウムは一度に大量に摂取するよりも、500mg以下の量を朝食と夕食など、1日の中で数回に分けて摂る方が体内での吸収効率が高まります。
一方で、加工食品に多い「リン」や、ほうれん草に含まれる「シュウ酸」、カフェインなどはカルシウムの吸収を妨げることがあるため、これらの過剰な摂取は避けるのが賢明です。
骨に効く運動ワザを習慣に
食事と並行して、骨に適度な刺激を与える運動を習慣にすることも、骨密度を維持する上で欠かせません。
「骨を刺激すること」と「転ばない体をつくること」の2点を意識した運動法を見ていきましょう。
骨密度を効果的に高めるには、骨に物理的な負荷をかける運動と、骨折の最大の原因である転倒を予防する運動の両方を実践することが重要です。
骨は、使って負荷をかけるほど、その刺激に反応して強く丈夫になる性質を持っています。
同時に、骨がもろくなっている状態での転倒は致命的な骨折につながるため、筋力とバランス感覚を養い、転びにくい体を作ることも不可欠です。
骨を直接刺激する運動として最も効果的なのは、自分の体重を骨にかける「ウェイトベアリング運動」です。
具体的には、ウォーキングや軽いジョギング、階段の上り下りなどが挙げられます。
また、その場でかかとを軽く上げ、ストンと落とす「かかと落とし体操」や、軽いジャンプも短時間で骨に刺激を与えられる優れた運動です。
さらに、スクワットなどの「レジスタンス運動(筋トレ)」は、筋肉が骨を引っ張る力を利用して骨を強化します。
転ばない体づくりのためには、「バランス運動」が中心となります。
片足立ちや、太極拳、ヨガといったゆっくりとした動きは、体幹を安定させ、バランス能力を高めるのに役立ちます。
運動後にはストレッチを行い、筋肉の柔軟性を保つことで、ケガの予防や姿勢の改善にもつながります。
これらの運動を続けるコツは、「1日1分から」でも良いので、とにかく始めることです。
家事の合間や通勤中など、生活のスキマ時間を見つけて体を動かす習慣をつけることが、将来の健康を守る大きな一歩となります。
医師に相談したいタイミング
日々のセルフケアも大切ですが、体に変化を感じた際には専門家である医師に相談することが安心への第一歩です。
ここでは、骨密度検査を検討すべき具体的なサインを挙げます。
身長の縮みや姿勢の変化、原因不明の腰痛など、特定のサインが見られた場合は、早めに医療機関で相談することが強く推奨されます。
これらの症状は、骨密度の低下が進行している、あるいはすでに自覚のない「静かな骨折」が体内で発生している兆候である可能性があるからです。
早期に発見し、適切な対応をとることが、将来のより大きな骨折を防ぐ上で極めて重要です。
具体的に、以下のようなサインに一つでも気づいたら、かかりつけ医や整形外科に相談することを検討しましょう。
- 若い頃に比べて背が縮んだ気がする
- 壁に背中をつけたとき、後頭部が壁につかなくなった(姿勢の前かがみ)
- 転んだり、軽く手をついたりしただけで骨折した経験がある
- 原因がはっきりしない背中や腰の痛みが続いている
- 両親のどちらかが、足の付け根などを骨折した経験がある(家族歴)
骨密度の検査は、主に「DXA(デキサ)法」というX線を用いた方法で行われます。
検査自体は数分で終わり、痛みも全く伴いません。
自分の骨の状態を正確に知ることで、生活習慣の改善にもより具体的に取り組むことができます。
まとめ
骨密度の低下を防ぐための食事法と運動法についてまとめました!
今回の内容は、特別な道具や難しい知識がなくても、日々の生活の中で少し意識を変えるだけで実践できることばかりです。
特に「かかと落とし体操」はテレビを見ながらでもできるので、今日からすぐに始められそうです。
食事も、納豆やヨーグルト、小魚など、普段から食卓にのぼる食材を組み合わせるのがポイントなので、無理なく続けられると感じました。
「静かな病気」だからこそ、早めの対策で将来の骨折リスクを減らしていきたいです。
最後まで読んで頂きありがとうございました。